七夕の短冊、保育園で「大人は何を書けばいいの?」と悩んだことありませんか。
子どもと一緒に願い事を書く機会は意外と多いですが、保護者や先生として、どんな内容がふさわしいのか迷う方も多いはずです。
この記事では、実際に保育園で使える大人の七夕願い事の例文や、みんなが書いたリアルなエピソード、さらに大人が短冊を書くときの注意点や、イベントを盛り上げる工夫までたっぷりご紹介します。
七夕の行事がもっと楽しく、思い出深くなるヒントが満載です。
どんな願い事が喜ばれるか、迷っている方はぜひ最後まで読んでみてくださいね。
保育園で大人が書く七夕の願い事例まとめ!迷った時におすすめの例文集
保育園で大人が書く七夕の願い事例まとめ!迷った時におすすめの例文集について解説します。
それでは、実際にどんな願い事が使えるのか例文も交えて紹介していきますね。
①保護者向けのシンプルな願い事例
保育園の七夕イベントで保護者が短冊に願い事を書くシーンって、実はちょっと悩みがちなんですよね。
「ほかのママやパパは何を書いてるんだろう…」と、少しドキドキしながら書く人も多いです。
そんな時におすすめなのが、シンプルで前向きな願い事です。例えば「家族みんなが元気に過ごせますように」や「子どもが毎日楽しく通えますように」など。
ポイントは、短くても気持ちが伝わる内容にすること。「○○ちゃんが元気に大きくなりますように」「家族で楽しい時間が過ごせますように」なども素敵ですね。
迷った時は、ストレートな気持ちを短く書くのが一番です。気取らず素直な言葉が、子どもにも伝わりますよ。
筆者としても、ありのままの気持ちが一番だと思います。「シンプル・イズ・ベスト」ですね。
②先生向けの気遣いのある願い事例
先生が短冊を書く場合は、子どもたちや保護者への思いやりが伝わる願い事がベストです。
例えば「みんなが元気いっぱいに大きくなりますように」「楽しい毎日が続きますように」など、子どもや家庭の幸せを願う言葉が喜ばれます。
他にも「○○組のおともだちが毎日笑顔で過ごせますように」「みんなで素敵な思い出が作れますように」など、クラスやグループに寄り添った表現も素敵です。
先生自身の健康やチームワークを願う内容もOK。「みんなで助け合いながら楽しく過ごせますように」といった一言もいいですよ。
先生の願い事には「優しさ」や「見守る気持ち」をこめると、より保育園らしい温かい雰囲気になりますね。
③家庭・家族に関する願い事例
保護者や先生どちらでも使えるのが、家庭や家族の健康・幸せを願うパターンです。
「家族みんなが健康でいられますように」「夫婦仲良く過ごせますように」「おじいちゃんおばあちゃんが元気でいられますように」など、具体的な対象を入れるとグッと温かみが増します。
また「家族旅行に行けますように」「みんなでおいしいごはんが食べられますように」といった、ちょっとした夢や楽しみも素敵な願い事になります。
短冊を見た子どもたちにも、「家族っていいな」と思える内容が良いですね。
筆者も「家族みんなが笑顔で過ごせますように」と毎年書いています。やっぱり、家族の幸せはみんなの願いですよね。
④仕事や健康に関する願い事例
大人ならではの願い事として、仕事や健康に関する内容も定番です。
「仕事がうまくいきますように」「無理せず健康に働けますように」「体調を崩さず過ごせますように」といった短冊は、同じ大人同士共感を呼ぶ内容です。
「子育ても仕事も両立できますように」「新しいことにチャレンジできますように」など、前向きな気持ちをこめるのも良いですね。
健康系の願い事は、自分だけでなく家族や同僚への思いやりも感じられます。
書き方に迷ったら、素直に「健康」や「仕事」のことを書いてOKです!筆者もよく「無理せず頑張れますように」と願いを込めています。
七夕の願い事を大人が書くときの注意点5つ
七夕の願い事を大人が書くときの注意点5つについて詳しく解説します。
保育園での七夕は子どもたちの行事。大人として、どんな点に注意したら良いのかチェックしてみてくださいね。
①子どもに配慮した内容選び
まず一番大切なのは、子どもに配慮した内容を選ぶことです。
七夕の短冊は、子どもたちも見たり読んだりすることが多いので、「誰かを批判する」「仕事の愚痴」など大人の本音すぎる内容は控えましょう。
できるだけ子どもたちが読んで前向きになれる、優しい気持ちになれる内容にするのがベストです。
例えば「○○ちゃんが元気に通えますように」や「みんなが笑顔でいられますように」といった、周りへの思いやりが伝わるものだと安心です。
筆者もつい仕事の悩みを書きそうになりますが、ここはグッと堪えて子ども目線を意識しています。
②ネガティブな表現は避けよう
願い事を書くときは、どうしても「○○が嫌だ」や「○○がなくなりますように」など、否定的な表現が出てしまいがちです。
でも、せっかくの七夕イベントなので、「○○になりますように」「楽しく過ごせますように」といったポジティブな表現に変換しましょう。
言葉ひとつで雰囲気がガラッと明るくなりますよ。
保育園のイベントだからこそ、ポジティブな気持ちをみんなで共有したいですね。
筆者も「~したい」「~になってほしい」と、前向きな言葉を心がけています。
③字のきれいさ・読みやすさも大切
大人が書く短冊は、やっぱり字のきれいさや読みやすさもポイントです。
あまりに雑だったり、小さすぎたりすると、せっかくの願い事も伝わりづらくなってしまいます。
丁寧な字でゆっくりと書くことで、子どもたちのお手本にもなりますし、気持ちもより伝わりやすくなります。
見やすいように、ひらがなやカタカナも積極的に使うのがおすすめです。
筆者もいつもよりゆっくりめに、一文字ずつ丁寧に書くようにしていますよ~!
④保育園らしいポジティブな雰囲気を意識
保育園の七夕は、子どもたちの「ワクワク」や「夢」を大切にしたいイベントです。
大人が書く願い事も、できるだけ保育園らしいポジティブな雰囲気を意識しましょう。
「みんなが笑顔で過ごせますように」「楽しい思い出が増えますように」など、明るい気持ちになれる言葉選びがおすすめです。
筆者も「笑顔があふれますように」とか、ちょっと前向きワードを盛り込むようにしています!
⑤短冊のスペースに収まる例文を
七夕の短冊って、実は意外とスペースが小さいんですよね。
長々と願いを書いてしまうと、入りきらなかったり、読みづらくなってしまったり…。
なので、短くても気持ちが伝わる一言にまとめるのがコツです。
どうしても伝えたい内容がある場合は、できるだけシンプルな言葉にギュッとまとめてみましょう。
筆者も毎回、「このスペースにどう収めるか…」と悩みながら書いてます。短くても想いは伝わるので安心してくださいね。
みんなが実際に書いた!大人の七夕願い事エピソード7選
みんなが実際に書いた!大人の七夕願い事エピソード7選についてご紹介します。
ここからは実際に保育園で大人がどんな願い事を書いてきたか、リアルなエピソードをたっぷり紹介しますね。
①先生の「子どもたちの成長を願う」例
まず多いのが、先生たちによる「子どもたちの成長」にまつわる願い事です。
たとえば「みんなが元気に大きくなりますように」「○○組のお友だちが毎日楽しく通えますように」「子どもたちがケガなく過ごせますように」など。
行事ごとにこの願い事を書く先生も多く、保育士さんならではの視点があふれています。
短冊を見ると、子どもたちへの愛情や日々の頑張りを感じられて、ほっこりしますよね。
先生の温かい言葉は、保護者や子どもたちにもしっかり届きます。筆者も「みんなが笑顔で過ごせますように」という願い、何度も見かけました!
②保護者の「家族円満を願う」例
保護者がよく書くのは、やっぱり家族や家庭の幸せを願う短冊です。
「家族みんなが健康で幸せに過ごせますように」「家族が毎日笑顔で過ごせますように」「みんなで楽しい思い出が作れますように」といった内容は王道。
ほかにも「パパとママが仲良くできますように」「おじいちゃんおばあちゃんとたくさん遊べますように」と、家族みんなへの想いを短冊に込める人も多いです。
こんな風に家族への感謝や願いを素直に書くことで、短冊を見た人の心も温かくなりますよね。
筆者も子どもが通園していたとき、「家族でたくさん笑えますように」と書いたことを思い出しました。
③「仕事の成功」系の例
意外と多いのが、仕事にまつわる願い事。
「仕事がうまくいきますように」「上司にほめられますように」「新しい職場でも楽しく働けますように」など、リアルな願いもよく見かけます。
「子育ても仕事も頑張れますように」「働きながら家族と楽しく過ごせますように」など、働く大人ならではの短冊も増えています。
大人も夢や希望を持っているという姿を、子どもたちに見せられる良い機会ですね。
筆者としても、親が自分の夢や努力を短冊に書くのは素敵だと思います!
④「健康・安全」系の例
コロナ禍以降、ますます増えたのが「健康」や「安全」に関する願い事。
「みんなが元気に過ごせますように」「ケガや病気をせずに毎日過ごせますように」「家族みんなが健康第一でいられますように」など。
「ウイルスに負けず、みんなが笑顔でいられますように」なんて短冊も最近はよく見かけます。
保育園という場だからこそ、健康や安全を第一に考える大人の願い事がたくさん集まっています。
筆者も「無事故で1年過ごせますように」と願いを込めて書いたことが何度もあります。
⑤「趣味・プライベート充実」系の例
大人の短冊には、「趣味」や「プライベート」にまつわる願いもたまに見かけます。
たとえば「家族でキャンプに行けますように」「趣味の時間を楽しめますように」「新しい友達ができますように」など。
子どもと一緒に体験したいことや、自分自身のささやかな夢を短冊に書くのも素敵ですよね。
みんなの前で堂々と書くのはちょっと勇気がいりますが、保育園の和やかな雰囲気ならアリだと思います。
筆者も「週末は家族でピクニックできますように」なんて書いてみたいな~とよく思います。
⑥「社会や平和への願い」系の例
ここ最近増えているのが、「社会」や「平和」に関する願い事です。
「世界が平和になりますように」「みんなが差別や争いなく暮らせますように」「困っている人が幸せになれますように」など。
子どもたちの前だからこそ、大人として「人に優しく」といった願いを書くのもとても素敵ですね。
保育園の七夕を通じて、社会全体や世界への想いを短冊に込める大人が増えている印象です。
筆者も、いつか「世界中の子どもたちが幸せでありますように」と書いてみたいと思っています。
⑦ユーモアあふれる願い事例
最後は、ちょっとユニークなユーモア系の願い事!
「毎朝スムーズに起きられますように」「ダイエットが成功しますように」「宝くじが当たりますように」など、笑っちゃう内容も意外と多いです。
子どもたちも先生も、ついクスッと笑顔になるような短冊は、イベントの雰囲気も明るくなります。
あまりふざけすぎはNGですが、ちょっとした笑いや「わかる~」と思ってもらえる内容は、むしろ好印象ですよ。
筆者も「毎日コーヒーをゆっくり飲めますように」なんて短冊、今度書いてみたいです!
保育園の七夕イベントを盛り上げる!大人も楽しめるアイデア5選
保育園の七夕イベントを盛り上げる!大人も楽しめるアイデア5選を紹介します。
七夕は子どもたちが主役の行事ですが、大人も一緒に楽しむことで、より思い出深いイベントになりますよね。
①親子で楽しむ短冊づくり
親子で一緒に短冊を作る時間は、七夕イベントの定番でありながら、やっぱり大人気です。
色紙やシール、マスキングテープなどを使って、世界にひとつだけのオリジナル短冊を作ると、それだけで子どもも大人もワクワクします。
自分で作った短冊に願い事を書くことで、イベントへの思い入れも深まりますし、親子の会話も自然と増えます。
保育園によっては、持ち帰りOKにしたり、飾りつけコンテストを行うところもあります。
筆者としても、親子で手を動かしながら「何書く?」と笑い合う時間は最高に思い出に残るので、全力でおすすめしたいです!
②先生・保護者の願い事発表タイム
大人も短冊に書いた願い事を、みんなの前で発表する「願い事発表タイム」も大人気です。
子どもたちが「ママはどんな願い事を書いたの?」「先生は?」と興味津々で耳を傾けてくれます。
大人が夢や目標を堂々と語ることで、子どもたちにも「願うことの大切さ」が伝わります。
照れくさい人は、先生や保護者同士でグループ発表にしたり、みんなで拍手する時間を作ってみるのもおすすめです。
筆者も発表会で子どもに「お母さんの願い事、素敵だね」と言われた時は、心がじんわり温かくなりましたよ。
③飾りつけワークショップ
七夕といえば、笹や星、カラフルな飾りもイベントの醍醐味ですよね。
大人も子どもも一緒に、折り紙や色紙で飾りを作る「飾りつけワークショップ」を行うと、教室が一気ににぎやかになります。
星や提灯、天の川など、みんなで工夫しながら作った飾りは、見ているだけで楽しい気持ちになります。
作品を持ち帰ったり、写真に撮って思い出に残すのもおすすめです。
筆者も折り紙が苦手ですが、子どもと一緒なら意外と夢中になってしまいます。「みんなで作るイベント」ってやっぱり楽しいですね。
④願い事にちなんだ絵本読み聞かせ
七夕にちなんだ絵本を読み聞かせる時間も、毎年大好評です。
「たなばたバス」や「たなばたさま」「おりひめとひこぼし」など、願い事や星にまつわるお話は子どもたちも大好き。
読み聞かせの後に「みんなの願い事は何?」と問いかけると、自然にコミュニケーションも広がります。
大人も絵本の世界に癒されつつ、子どもと一緒に夢や願いを考えるきっかけになりますよ。
筆者も絵本読み聞かせ担当のときは、ちょっと緊張しますが、子どもたちの真剣な顔に元気をもらいます。
⑤みんなで歌う七夕の歌タイム
イベントの最後は、みんなで「たなばたさま」など七夕の歌を歌って締めくくるのがおすすめです。
歌うことで会場の一体感も高まりますし、音楽の力で「みんなの願いが叶いそう!」な明るい雰囲気に包まれます。
楽器を使ったり、手拍子やダンスを取り入れても盛り上がりますよ。
最後にみんなで「お願いごとがかないますように!」と声を合わせて、笑顔でイベントを終えると、最高の思い出になります。
筆者も「たなばたさま」を歌うと、子ども時代に戻ったような気持ちになるので、毎年楽しみにしています!
大人が書いても浮かない!保育園の七夕でおすすめしないNG例とその理由
大人が書いても浮かない!保育園の七夕でおすすめしないNG例とその理由について解説します。
せっかくの七夕行事。大人が書く願い事も、周囲の雰囲気や子どもたちへの配慮を意識したいですね。
①個人的すぎる願い事
まず気をつけたいのが、あまりに個人的すぎる願い事です。
例えば「宝くじが当たりますように」「恋人ができますように」など、プライベート感満載の内容は、保育園という場には少し浮いてしまうかもしれません。
もちろん、絶対NGというわけではありませんが、みんなが読む場所に飾る短冊は、できるだけ子どもや周囲に共感してもらえる内容が安心です。
どうしても書きたい場合は、表現をやわらかくしたり、「みんなが幸せに」「家族が笑顔で」など周囲にも配慮した内容に工夫してみてください。
筆者も個人的な願いを書きたい時は、少しオブラートに包んでいますよ。
②ネガティブ・愚痴っぽい願い事
「上司に怒られませんように」「仕事がつらくなくなりますように」など、ネガティブな内容や愚痴っぽい願い事は場にそぐわない印象を与えがちです。
短冊はみんなが読むものなので、暗い気持ちや重たい話題は避けるのがベターです。
できるだけ「楽しく働けますように」「新しいチャレンジができますように」など、ポジティブな言い回しに変換しましょう。
願い事の言葉選びひとつで、イベントの雰囲気も明るくなります。
筆者もたまに愚痴っぽくなりそうなときは、前向きな表現に置き換えてみています!
③子どもが不安になる表現
「病気が治りますように」「いじめがなくなりますように」といった表現は、大人としては切実な願いでも、子どもが読むと不安になってしまう場合があります。
特に保育園の短冊は子どもたちの目に触れることが多いので、子どもたちが安心して読める内容にすることが大切です。
健康や安全を願う場合も、「みんなが元気でいられますように」「楽しく過ごせますように」といった、明るい言い方に変えてみてください。
不安をあおるような言葉は避けると、イベントもより和やかな雰囲気になりますよ。
筆者も子どもたちの顔を思い浮かべながら、言葉選びには気をつけています!
④場違いな内容やジョーク
イベントを盛り上げたいあまり、ついふざけたジョークや場違いな内容を書いてしまうことも。
例えば「給料が倍になりますように」「ダイエットしなくて済みますように」など、ちょっと笑いをとりたくて書きたくなる気持ちも分かります。
ですが、保育園という場では、周囲への配慮も大切です。
ジョークを入れる場合も、子どもや保護者、先生みんなが思わず笑顔になるような、ほっこり系の内容にすると安心です。
筆者もユーモアを入れたい時は、「みんなが毎日笑顔で過ごせますように」など、ポジティブな方向に仕上げるよう心がけています。
まとめ|七夕 願い事 例 大人 保育園で迷わない!ポイントとおすすめ例
七夕の願い事、保育園で大人が書くときに「どんな内容がいいかな?」と悩んだら、まずは子どもや家族、みんなの幸せを願う例文から選んでみてください。
シンプルで前向きな言葉や、周囲への思いやりが感じられる内容がいちばん安心です。
また、ネガティブな表現や個人的すぎる内容、子どもが不安になる言葉や場違いなジョークには気をつけましょう。
保育園の七夕イベントは、大人も一緒に楽しめる特別な時間。みんなで思い出に残る願い事を書いて、素敵な七夕を過ごしてくださいね。
参考情報として、保育園行事や七夕の願い事については保育園での七夕|行うねらい・事例・準備などを紹介!や、保育のお仕事「七夕短冊の願い事例」もぜひご覧ください。
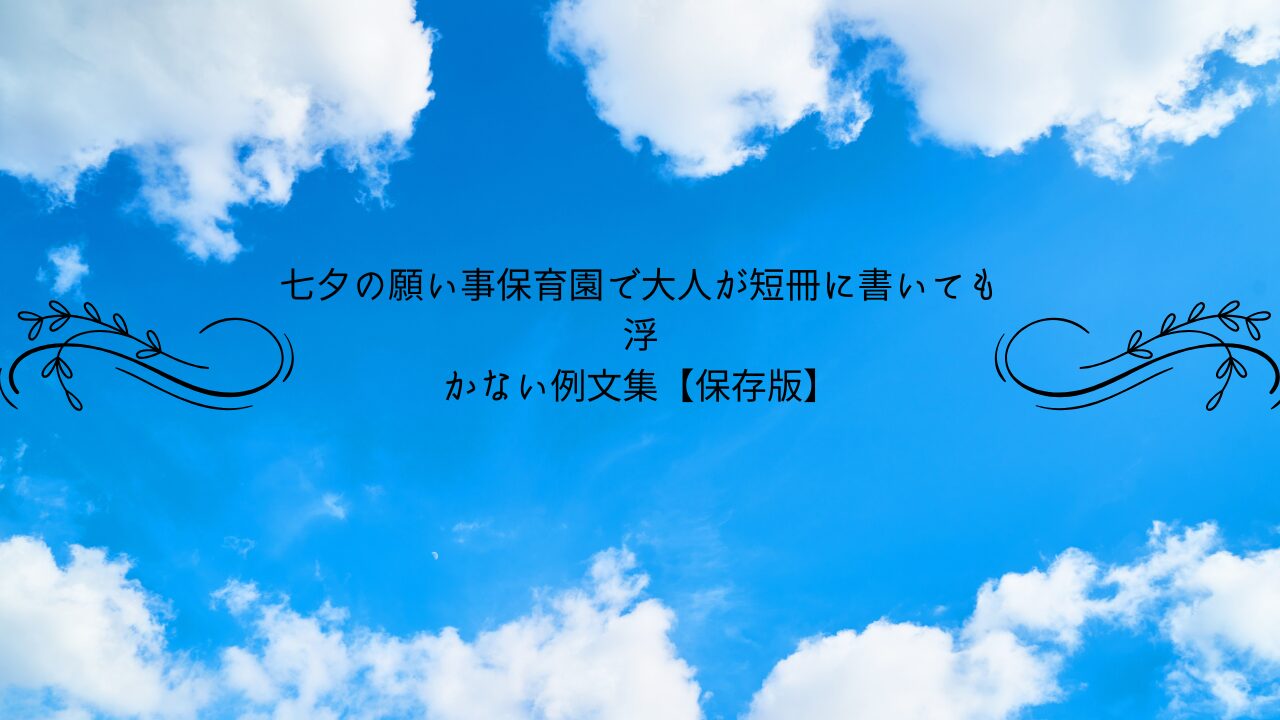


















コメント